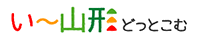гҖҖзҡҗжңҲгҖӮ
гҖҖжЎңгҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰе’ІгҒҚд№ұгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮөгӮҜгғ©гғігғңгҖҒгғӘгғігӮҙгҖҒгғ–гғүгӮҰгҖҒгғ©гғ•гғ©гғігӮ№гҖҒгғўгғўгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжһңжЁ№гҒ®иҠұгҖ…гӮӮеӨ§еһӢйҖЈдј‘гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еҺ»гҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰиҗҢй»„иүІгҒ®еӯЈзҜҖгҒҢиЁӘгӮҢгҖҒз–ІгӮҢгҒҹзӣ®гӮ’зҷ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶе„ӘгҒ—гҒ„з·‘гҒҢжңЁгҖ…гӮ’иҰҶгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҲеұұгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒйҒ гҒҸгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢжңқж—ҘйҖЈеі°гҒ®еұұдёҰгҒҝгҒҜдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰзңҹгҒЈзҷҪгҒӘй ӮгӮ’йқ’з©әгҒ«гҒҸгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁжө®гҒӢгҒ°гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ®еұұгҖ…гҒҜж—ҘгҖ…иүІеҗҲгҒ„гӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е№јеӯҗгҒҢе°‘е№ҙе°‘еҘігҒ«иӮІгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ
й»„иүІе‘ігҒҢ次第гҒ«и–„гӮҢз·‘гҒ®иүІеҗҲгҒ„гҒҢжҝғгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еұұеҪўгӮ„еӨ©з«Ҙе‘ЁиҫәгҒ§гҒҜгҖҒжҷ©жҳҘгҒӢгӮүеҲқеӨҸгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®гҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«дёҮзү©гҒҢжҒҜеҗ№гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢж„ҹгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖгҒқгӮ“гҒӘдёӯгҒ§гҖҒиҝ‘йғҠгҒ®з”°гӮ“гҒјгҒ§гҒҜз”°жӨҚгҒҲгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒ гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеӨ§еҚҠгҒ®з”°гӮ“гҒјгҒҜгҒҹгҒ ж°ҙгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгҒ гҒ‘гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒӢгӮүзңәгӮҒгӮӢгҒЁгҒ“гӮҢгҒҢе®ҹгҒ«зҫҺгҒ—гҒ„гҖӮ
еұұеҪўзӣҶең°гҒ«е·ЁеӨ§гҒӘж№–гҒҢеҮәзҸҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁйҢҜиҰҡгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ
жқұиҘҝ10ж•°гҢ”гҖҒеҚ—еҢ—40ж•°гҢ”гҒ®гҒ“гҒ®зӣҶең°гҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁж№–гҒ гҒЈгҒҹгҒЁиҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йқўз©ҚгҒҜзҗөзҗ¶ж№–гҒ®4еҲҶгҒ®3иҝ‘гҒҸгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҒқгҒ®еәғеӨ§гҒ•гҒҜжғіеғҸгҒҢгҒӨгҒҸгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еӨ©з«ҘгҒ®еҢ—гҒ®ж–№гҒ«гҒӮгӮӢжқ‘еұұеёӮгҒ®зӢӯйҡҳгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§жңҖдёҠе·қгҒҢгҒӣгҒҚжӯўгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒӢгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜдјқиӘ¬гҒ§гҖҒжңүеҗҚгҒӘгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢгҒқгҒ“гӮ’еҲҮгӮҠй–ӢгҒҚеәғеӨ§гҒӘз”Ёең°гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еӨҡеҲҶеӨ§ең°йңҮгҒ«гӮҲгӮӢең°ж®»еӨүеӢ•гҒ§гҖҒгҒӣгҒҚжӯўгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹеұұгҒҢеҙ©гӮҢгҖҒж°ҙгҒҢжөҒгӮҢеҮәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢзңҹзӣёгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰиЎ“зҡ„гҒ«гҒҜиӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҹгҒ гғӯгғһгғігҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе®ҹйҡӣгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’иӘҝгҒ№гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҮҺжҡ®гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
йқўзҷҪгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҖҒең°еҗҚгҒ«е·ЁеӨ§ж№–гҒ®еҗҚж®ӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жқұгҒ®еұұгҒҷгҒқгҒ«гҖҢжқұж №гҖҚгҖӮ
гӮөгӮҜгғ©гғігғңгҒ§жңүеҗҚгҒӘжқұж №еёӮгҒ§гҒҷгҖӮ
иҘҝгҒ®гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁе°Ҹй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«еҜ’жІіжұҹеёӮгҒ®гҖҢиҘҝж №гҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹжқұж №еёӮгҒЁжқ‘еұұеёӮгҒ®еўғгҒ®еұұгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒиҚ·жёЎгҒ—ең°и”өгҒҢзҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж°ҙгҒЁгҒҜе…ЁгҒҸй–ўдҝӮгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒе·ЁеӨ§ж№–гҒ®дјқиӘ¬гӮ’зҹҘгӮӢгҒҫгҒ§гҒҜгҒӘгӮ“гҒ§гҒ“гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒЁдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иҲӘиЎҢгҒ®е®үе…ЁгӮ’зҘҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зҘҖгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӯгҖӮ
гғ“гғ«гӮ„дәә家гҒҢз«ӢгҒЎдёҰгҒ¶зҸҫеңЁгҒ®е…үжҷҜгӮ’зӣ®гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒӮгӮүгҒҢгҒ„гӮҲгҒҶгҒ®гҒӘгҒ„еӨ§иҮӘ然гҒ®еЁҒеҠӣгӮ„гҒ“гҒ“гҒҫгҒ§зҜүгҒҚдёҠгҒ’гҒҰгҒҚгҒҹдәәй–“гҒ®жӯҙеҸІгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гҒӘгҒ©жғігҒ„гҒҜжһңгҒҰгҒ—гҒӘгҒҸеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҒӘгӮ“гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮеұұиҸңгҖӮ
з”Јзӣҙж–ҪиЁӯгҒӘгҒ©гҒ«гҒҜгҖҒгғҜгғ©гғ“гҖҒгӮігӮҙгғҹгҖҒгӮҰгғүгҖҒгӮігӮ·гӮўгғ–гғ©гҖҒгӮҝгғ©гҒ®иҠҪгҖҒжңЁгҒ®иҠҪгҒӘгҒ©гҒҢйҖЈж—ҘйҒӢгҒ°гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёӯгҒ«гҒҜгҒ“гӮҢдҪ•гҒЁгҒ„гҒҶеҗҚеүҚгҒӘгҒ®гҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰйЈҹгҒ№гӮӢгҒ®гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж—ҘгҒ”гӮҚгҒӮгҒҫгӮҠгҒҠзӣ®гҒ«гҒӢгҒӢгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ©гӮҢгӮӮеұұйҮҺгҒӢгӮүгҒ®вҖңзӣҙиЎҢе“ҒвҖқгҖӮ
е‘ігӮ„йҰҷгӮҠгҒҜпјҹиЁҖгҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ