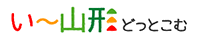иҸңең’гҒ®з§ӢеҶ¬зү©йҮҺиҸңгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒжң¬еҪ“гҒ«з§ӢгҒҢзҹӯгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’з—ӣж„ҹгҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жәҖи¶ігҒ«жҲҗй•·гҒ—гҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ«еҶ¬гӮ’иҝҺгҒҲгҒҹе§ҝгҒҜгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢз—ӣгҒҫгҒ—гҒҸгҖҒгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁиӮІгҒҰгҒҰгӮ„гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«жғ…гҒ‘гҒӘгҒ•гҒҢиҫјгҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҷгҒ№гҒҰгҒҢжё©жҡ–еҢ–гҒ«гӮҲгӮӢз•°еёёж°—иұЎгҒ®гҒӣгҒ„гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҜ’гҒ•гҒҢеў—гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹз•‘гҒ®дёӯгҒ«з«ӢгҒЎе°ҪгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠвҖңй«ҳжё©вҖқгҒёгҒ®жҒЁгҒҝгҒҢеӢҹгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҖгӮӨгӮігғігӮ„зҷҪиҸңгҖҒгӮ«гғ–гҒӘгҒ©з§ӢеҶ¬зү©йҮҺиҸңгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜ8жңҲгҒ«зЁ®гӮ’и’”гҒҸгҒ®гҒҢйҒ©еҪ“гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ“ж•°е№ҙгҖҒз•°еёёгҒӘгҒ»гҒ©гҒ®й«ҳжё©гҒ§иҸңең’гҒ®еңҹгҒҜж’ӯзЁ®гҒ«йҒ©гҒ•гҒӘгҒ„жё©еәҰгҒ«гҒҫгҒ§дёҠжҳҮгҒ—зҷәиҠҪгҒ—гҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зЁ®гӮ’и’”гҒҸжҷӮжңҹгӮ’еҫҢгӮҚгҒ«гҒҡгӮүгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒзҷәиҠҪгҒҜжҸғгҒҶгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒд»ҠеәҰгҒҜз”ҹиӮІжңҹй–“гҒҢи¶ігӮҠгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
ж Ҫеҹ№гҒ®гӮ№гӮҝгғјгғҲжҷӮгҒҜжҡ‘гҒҷгҒҺгҒҰиҠҪгҒҢеҮәгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸиӮІгҒЎе§ӢгӮҒгҒҹгҒЁжҖқгҒЈгҒҹгӮүгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒ—гҒҰж°—жё©гҒҢжҖҘжҝҖгҒ«дҪҺдёӢгҒ—гҖҒз”ҹиӮІгҒҢйҲҚгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ
з”ҹиӮІжңҹй–“гҒҢзҹӯгҒҷгҒҺгҒҰгҖҒзҷҪиҸңгӮ„гӮӯгғЈгғҷгғ„гҒӘгҒ©гҒҜзөҗзҗғгҒҢгҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ—гҖҒеӨ§ж №гӮ„гғӢгғігӮёгғігҒҜжҷ®йҖҡгҒ®й•·гҒ•гӮ„еӨӘгҒ•гҒҫгҒ§еұҠгҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з”ҹиӮІжңҹй–“гҒҢзҹӯгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеңҹдёӯгҒ®е®іиҷ«гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҘеүҚгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰе®іиҷ«иў«е®ігӮӮж јж®өгҒ«еў—гҒҲгҖҒең°йҡӣгҒ§иҢҺгҒҢйЈҹгҒ„иҚ’гӮүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгӮ„гҒҹгӮүзӣ®з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹиӮІз’°еўғгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҹдёӯгҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒӢгҖӮ
е‘ЁеӣІгҒ®з•‘гӮ’зңәгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒеӨҡгҒҸгҒҜгӮҸгҒҢиҸңең’еҗҢж§ҳгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒе…Ёе“ЎгҒҢиЁҺгҒЎжӯ»гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгӮүгҒ—гҒ„йҮҺиҸңгӮ’еҸҺз©«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе§ҝгӮӮиҰӢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е№ҙгҒ”гҒЁгҒ«зҹӯгҒҸгҒӘгӮӢз”ҹиӮІжңҹй–“гӮ„еў—гҒҲгӮӢе®іиҷ«гҒӘгҒ©гҒЁгҒ©гҒҶжҲҰгҒҶгҒӢгҖҒзҷҪгҒ„дё–з•ҢгҒҢеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢй–“гҒ«и…°гӮ’жҚ®гҒҲгҒҰгҒҳгҒЈгҒҸгӮҠжҺўгҒЈгҒҰгҒҝгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢжҜҺж—ҘгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒгҒқгҒ®иҫәгҒҜеӨ§дёҲеӨ«гҖҚ
д№қе·һгӮ„жІ–зё„гҒ®еҸӢдәәгҒӢгӮүгҒҸгӮӢйӣ»и©ұгҒ®й–ӢеҸЈдёҖз•ӘгҒҜз•°еҸЈеҗҢйҹігҒ«гӮҜгғһеҮәжІЎгҒ®и©ұгҒ§гҒҷгҖӮ
еҜ’гҒ•гҒҢеў—гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮүе°‘гҒ—гҒҜеҸҺгҒҫгӮӢгҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ©гҒҶгӮ„гӮүз”ҳгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒзӣёеӨүгӮҸгӮүгҒҡеёӮеҪ№жүҖгҒӘгҒ©гҒӢгӮүеҮәжІЎжғ…е ұгҒЁжіЁж„Ҹе–ҡиө·гҒ®гғЎгғјгғ«гҒҢжөҒгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еёӮиЎ—ең°гҒӘгҒ©гҒ§гҒ®зҢҹйҠғгҒ®зҷәз ІгҒҜеҚұйҷәеәҰгҒҢй«ҳгҒҸеҺігҒ—гҒҸиҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—дҪҸе®…иЎ—гҒ§гҒ®гӮҜгғһгҒ«гӮҲгӮӢдәәзҡ„иў«е®ігҒ®жӢЎеӨ§гҒ«дјҙгҒ„гҖҒж”ҫзҪ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ«гҒҫгҒ§иҝҪгҒ„иҫјгҒҫгӮҢгҖҒз·ҠжҖҘйҠғзҢҹгҒ®жҺӘзҪ®гӮ’ж–ҪгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
е…ҲжңҲдёӯж—¬гҒ«д»ҷеҸ°еёӮгҒ§е…ЁеӣҪеҲқгҒ®з·ҠжҖҘйҠғзҢҹгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзңҢеҶ…гҒ§гҒҜд»ҠжңҲжң«гҒҫгҒ§гҒ«14й ӯгҒҢй§ҶйҷӨгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҜгғһгҒ®жҚ•зҚІгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒгғһгӮҝгӮ®гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҢҹеё«гҒҹгҒЎгҒҢеұұж·ұгҒҸеҲҶгҒ‘е…ҘгҒЈгҒҰиЎҢгҒҶгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒҫгҒ•гҒӢдҪҸе®…гҒ®еәӯе…ҲгҒ«гҒӮгӮӢжҹҝгҒ®жңЁгҒ®дёҠгҒ§ж¬ЎгҖ…гҒЁй§ҶйҷӨгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒҜгҖӮ
жҹҝгҒ®е®ҹгҒӘгҒ©гҒҜгҒҫгӮӮгҒӘгҒҸе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«зӢҷгҒҶйӨҢгҒҜдҪ•гҒӘгӮ“гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒ„гҒҸгӮүеӯҰзҝ’иғҪеҠӣгҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгӮҜгғһгҒ§гӮӮгҖҒгҒҫгҒ•гҒӢйЈҹж–ҷе“Ғеә—гҒ«зӣ®гӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒйҖЈгӮҢз«ӢгҒЈгҒҰгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гӮ“гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӯгҖӮ
пјҲ2025/11/30гҖҖиҫ»и•ҺйәҰHPпјү